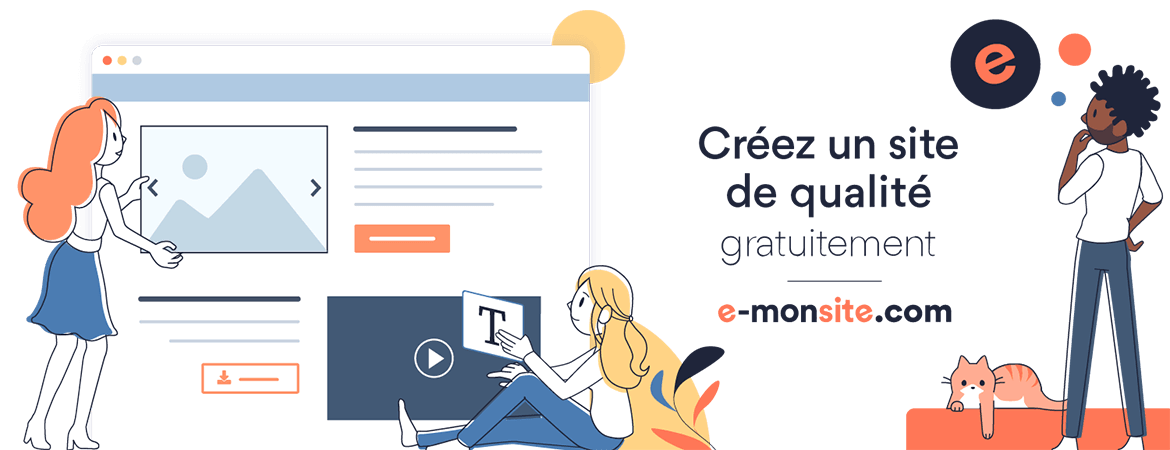「わしの望みは、姫様のお子を、この手に抱くことであった」
二人が立つ一丈ほど下の潅木の根元を縫うように、山案山子がするすると横切った。
「帝から、姫様を女御にと望まれた」
あごを上げ、老臣に目をやった。
老臣は、うつろな目で前方を見やっていた。
「姫様の評判が、内裏に届いていても不思議ではない。むろん、今上帝の生母であり主人の伯母君からの推挙もあろうがな」
国司が、この地に流された理由の一つが、先の帝に矢を射かけたことだと訊いている。
今生帝は、そのような男の姫をそばに置こうというのか。人の考えることが理解できなかった。
それを察したように老臣が続けた。
「権勢を欲しいままにする左大臣を牽制する意味もあるのだろう。とはいえ、大変な名誉だ……若すぎると思うやも知れぬが、十や十二での入内も珍しいことではない」
言葉とは裏腹に老臣は沈痛な表情を浮かべていた。【改善脫髮】四招避開活髮療程陷阱,正確生髮! -
イダテンの視線に気がつくと、老臣は、ああ、とつぶやいた。
言葉の意味が分からないと思ったのだろう。
「われらでいうところの妻だと思えば良い……しかし、帝には、すでに后がおいでになる」
そんなことが訊きたいのではない。
「断ることもできようが……そのようなことをしたらどのようなことになるか……大臣の位にない者の姫君を女御とするのは異例のことだ。帝の御不興はいうまでもなく、左大臣が、それを利用して、さらに追い討ちをかけてこよう」
それを俺に話してどうなるというのだ。
「……主人を追い落とした左大臣にも姫君がある。当然、入内させるつもりであろう」
だが、老臣はイダテンの気持ちに気づく様子もない。「たしかに、姫様が子をなし、その子が皇子で、やがて帝に即位しようものなら、主人を失脚させた左大臣を……あの男を追い落とせよう――主人は、この話に舞いあがっている。これで都に帰ることができようと。が、ことはそのように単純ではない……左大臣の権勢には、今や、帝と言えども逆らえぬ。何よりも……」
老臣の顔がゆがんだ。
「姫様が入内しようものなら……万が一にも、子をなさぬようにと、あらゆる手を打ってくるだろう」
毒を盛られると言うのだろう。
イダテンとおばばも、それで殺されかけたことがある。
左大臣とやらが命じなくても、その意を酌んで動く者もいるにちがいない。
老臣のこめかみの血の管が膨れ上がった。
「国親の動きも活発になってきた。近隣の郷司、保司に頻繁に人をやり、贈り物などを届けておるようだ。その折に、繋ぎをつけておるに違いない」
ありもせぬ謀反を収めたとして、うまい汁を吸った男だ。
二度目があっても不思議ではない。
だが、繰り返せば疑われるのではないか。
老臣は、わかっているとでもいうようにうなずいた。
「国親の郎党どもが、領地も荘園も増えたというのに、われらの実入りが増える様子もない、と、愚痴をこぼしておる……戦の支度じゃ。馬や鎧に銭をかけておるに違いない」
老臣が何を言いたいかは予測がつく。が、あえて問うた。
「国司が都に帰るとなれば、考え直すのではないか」
イダテンの言葉に老臣は首を振った。「左大臣は帰したくないのじゃ。国親は、それを承知で動いておるのだ。左大臣とつなぎをとっているとみて間違いあるまい……」
そもそも左大臣は、姫の父をこの地にとどめるつもりなどなかったのだ――船越の郷司一党を葬った国親を焚きつければ、すぐに片がつくと思っていたに違いない。
しかし、国親は動けなかった。
イダテンの母の呪詛に倒れたからだ。
愚痴を聞かせるために呼び出したのではあるまい。
にもかかわらず、老臣は、東に見える御山荘山の稜線に目をやったまま黙り込んだ。
しばらくして、誰に聞かせるふうでもなく呟いた。
「姫様は、この世に生を受け、名を与えられたそのときより、その呪力に縛られたのだ」
そして、向き直った。
挑むような、その目は血走っていた。